医大生に暇なし!?勉強や部活、バイトで大忙し

みなさん、大学生に対してどんなイメージを持っていますか?
暇?忙しい?
私の周りですと、医学部の学生は一般的に忙しいと思われていることが多いです。
結論を先に言うと暇かどうかは人によりますが、今回は6年間の医学部の大学生活について説明していこうと思います。

大学1年生
一般的に医学部の大学一年生は数学や物理、化学、生物、英語や第二外国語などの一般教養の科目を勉強します。大学にもよりますが、医学部生しか受けない授業の場合、医学に絡んだ授業になることが多いです。
また、一般教養が終わると基礎医学の勉強が始まります。生化学や生理学、組織学、解剖学などを勉強します。特に、生化学や生理学は人に特化した生物の勉強の延長のように感じられます。学生の中には基礎医学に苦手意識を持つ者や、臨床とのつながりを感じられずつまらないと思う者もいますが、医師になってからも、ものすごく大事知識となるので、しっかりと勉強することをおすすめします。
これらに部活やバイトも入ってくるので、予定をどれだけ入れるかで大学生活の忙しさは変わってきます。
しかし、勉強面で考えると、一年生は一番テストも楽で、長期休みも長いことが多いです。1年生のうちに沢山遊ぶのがおすすめです。
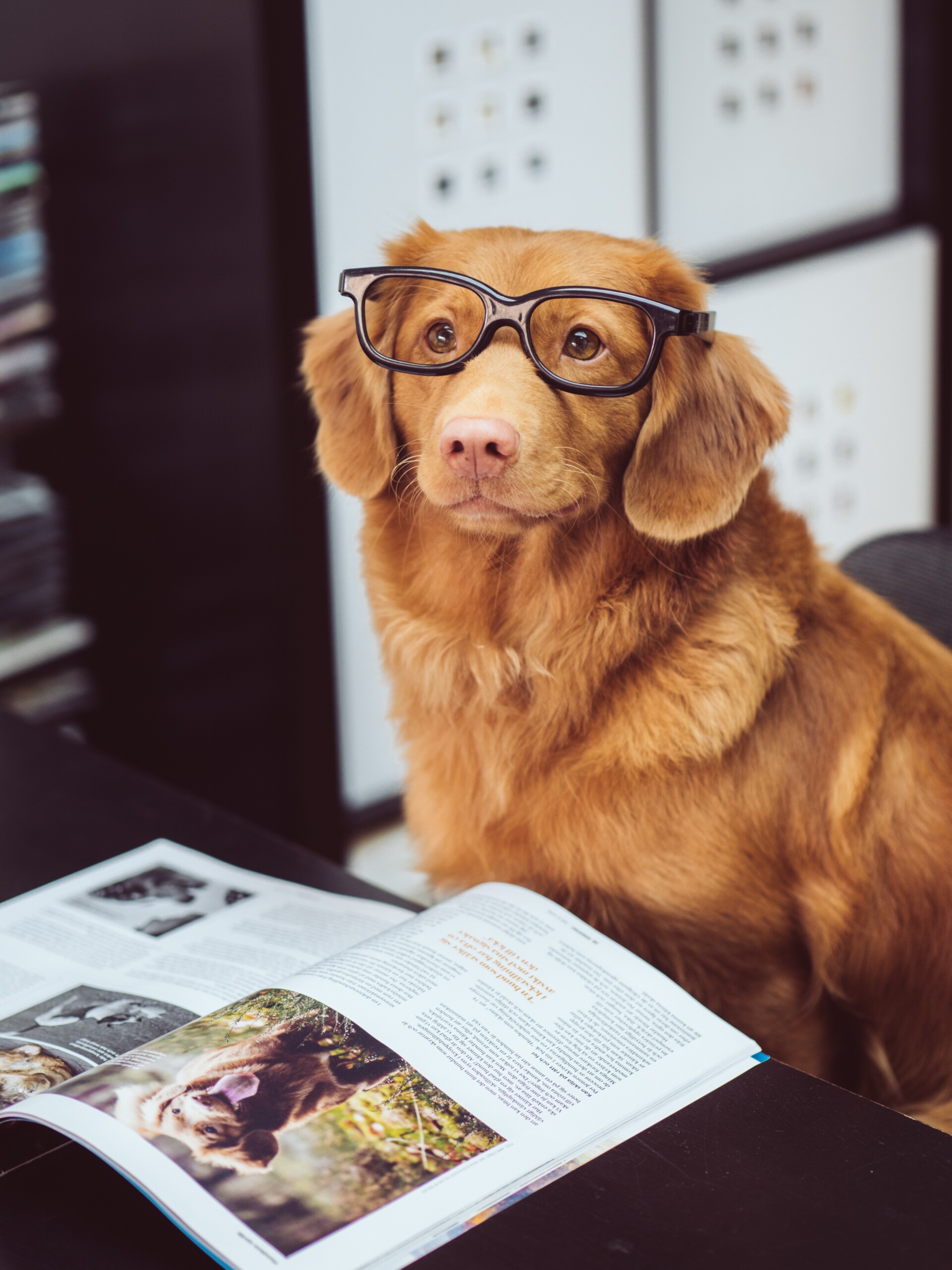
大学2年生
多くの医学部では大学2年生で解剖実習が始まります。大変さは大学にもよると思いますが、どの医学部に聞いても皆、口をそろえてとても勉強になると同時に大変だったといっていることが多いです。大学2年生の山場はここだと思います。解剖実習中だけバイトを休んでいる生徒もいました。
また、基礎医学の勉強も行います。一年生同様に生化学、生理学、解剖学を受講したり、免疫学や微生物学等を受講したりします。基礎医学の科目や勉強時期は大学によって違うので、具体的に知りたい方は「○○大学 医学部 カリキュラム」等で検索してみてください。どれから勉強しても大差はない気がします。
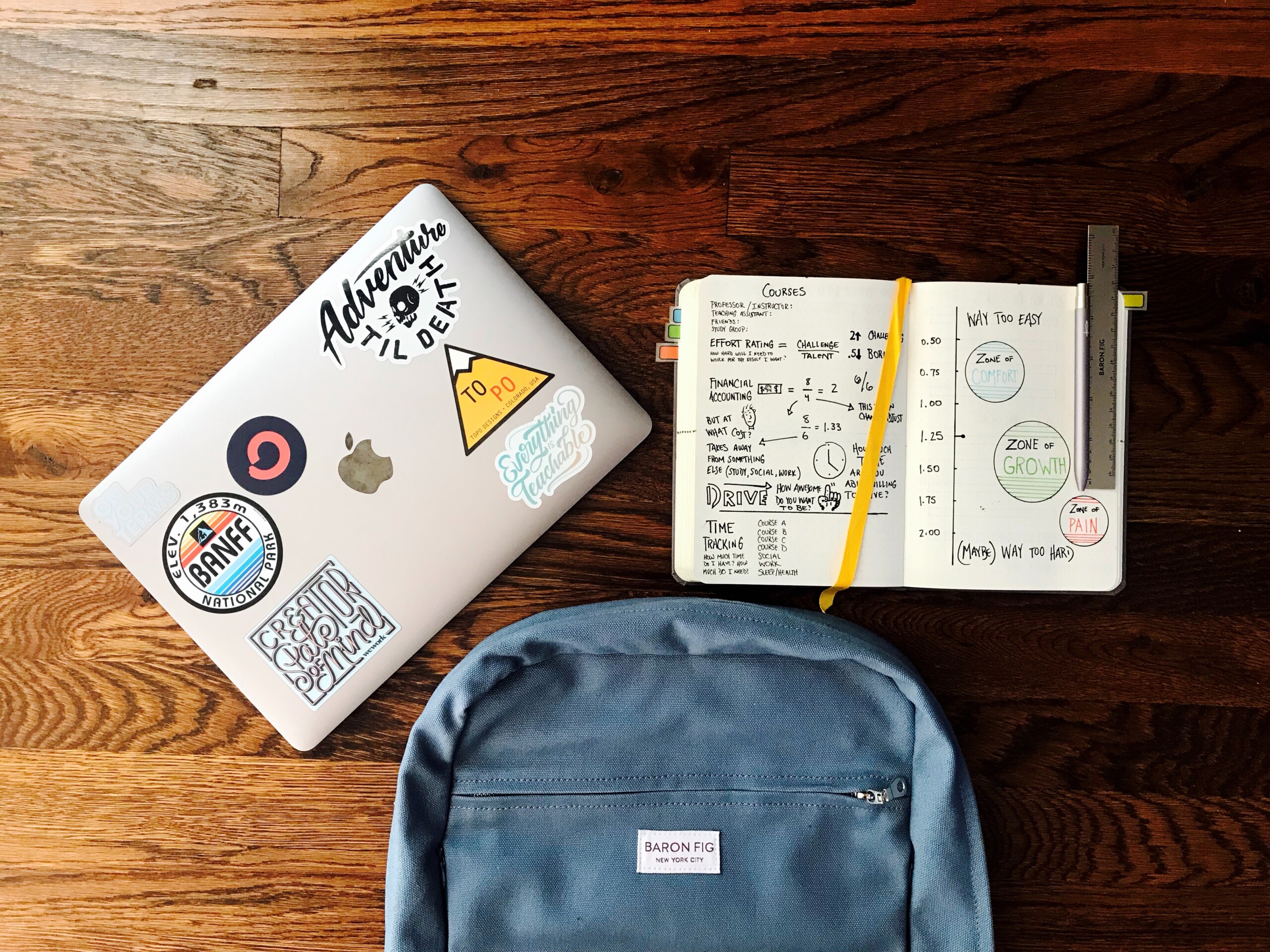
大学3年生~4年生
基礎医学が終わると、臨床医学の勉強が始まります。大学にもよりますが、3年生になる前後で始まるところが多いです。臨床医学とは、患者さんを診断、治療する医学分野のことです。臓器別に機能や疾患について勉強していきます。覚える量が一気に増えるので勉強が大変になっていきますが、医大生は臨床医学をやりたくて来ている人が多いので授業が楽しいと思えるようになった人も多いみたいです
そして約1年半ほどかけて臨床医学を勉強すると、大学4年生でOSCEとCBTという共用試験を受けます。これは全国の医学生が受ける者で、合格するとスチューデントドクターの認定を受けられます。これは、診療参加型実習に参加するために必要なものです。
OSCEとはObjctive Structured Clinical Examination(客観的臨床能力試験)のことで、医療面接や手技などの基本的臨床能力を評価する実技試験です。オスキーと呼びます。大体、大学4年生の夏から春にかけて行われます。全国の医学生が受ける試験ですが、大学によって試験日も試験内容もバラバラです。
CBTとはComputer Based Testの略で、医学部特有の言葉ではないので聞いたことがある人もいるかもしれません。名前の通り、パソコンで受ける試験です。シービーティーと呼びます。これは医学的な知識を評価する試験で、基礎医学から臨床医学、社会医学の範囲などから出題されます。これもOSCE同様、大学によって試験日はバラバラです。試験内容は一人一人違います。
軽く試験のアドバイスをしますと、OSCEもCBTも焦らないことが大事です。OSCEは時間が短いため、CBTは320問中80問が新問で採点されない上に難しいため試験日は焦りがちです。
これらの試験に合格し、晴れてスチューデントドクターの認定を受けると診療参加型実習が始まります。
医学部の部活は3,4年生が幹部(部長や会計など全体の運営)を務めることが多く、勉強に部活に最も大変な時期となることも多いです。

大学5年生
大学5年生になると参加型臨床実習が始まります。これらはポリクリ、クリクラと呼ばれることが多いです。ポリクリはドイツの臨床実習の通称であるポリクリニックの、クリクラはアメリカの臨床実習の通称であるクリニカルクラークシップの略称名です。最近は参加型実習の期間を早める傾向があるので4年生の後半の内に始まることが多いです。
この頃になると、実習する科によって集合時間、終了時間、忙しさなどが変わってくるためバイトの予定がうまく組めなくなってきます。そのため、週1から入れるバイトや時間に左右されないバイト、シフトの融通が利くバイトをしている生徒が多い印象があります。5年生になってバイトをやめる生徒も多いです。
大学6年生
いよいよ国家試験が近づいてくる学年です。大学は前期は実習がメインで、後期から授業も本格的に勉強にシフトしていきます。
国家試験の勉強を始める時期は人によりけりですが、多いのは5年生の冬~5月ごろでしょうか。もちろんもっと早い人もいますがこれより遅い人の割合は少ないです。
大学が勉強だけでは足りないと感じ、国家試験専門の予備校を受講し、過去問集をひたすら解き続ける人が多いです。これをやるためにはやはり、大学が勉強にシフトするより先に勉強を始めなくてはなりません。
6年生になるとバイトや部活をやめる人はさらに増えます。続ける人もいますが、かなり少なく、バイトや部活を行う頻度も減っている印象です。
とにかく、試験範囲が膨大なため、勉強に忙しくなります。
以上、医学部の大学6年間の生活について軽く紹介していきましたいかがだったでしょうか。
医学部の大学は高学年になるにつれ、勉強が忙しくて他のことに時間を割けなくなってきます。低学年の内からやりたいことは挑戦し、遊び、適度に勉強も行い充実した学生生活を送ってください。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。




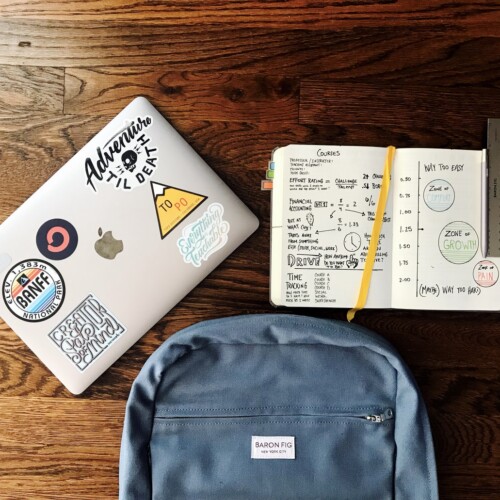






この記事へのコメントはありません。