医師の働き方改革とは?2024年から法律の施行がスタート!!
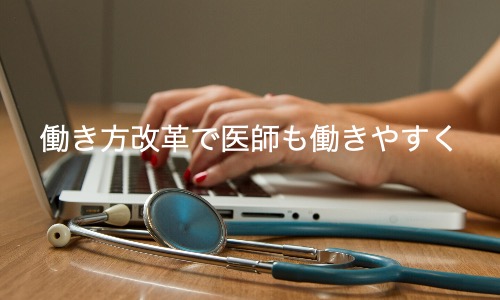
日本の社会全体で浸透しつつある「働き方改革」。皆さんも一度は聞いたことがあると思います。
医療現場でも「働き方改革」は広がりつつあります。
受験生の皆さんは、働くことに馴染みがあまり無いかもしれませんが、今回は医師の働き方について一緒に考えていければと思います。
Contents
医師の働き方改革は2024年から開始
近年進んでいる働き方改革は、ついに医師にも適用されることになりました。
コロナ禍での医療者、特に医師の労働の厳しさを受け、2021年5月に医師の働き方改革の実現に向けた改正医療法が成立しました。この改正医療法は、医師の健康確保のために、勤務間インターバルや面接指導、連続勤務時間の制限などを義務づけています。
では具体的にどのような働き方になるのか見ていきましょう。
①時間外労働の上限は1日平均4時間以内に(年間で960時間以下・月100時間未満)
もともと、労働基準法第32条で定められた労働時間は『1日8時間・週40時間まで』となっています。しかし医療者である以上、目の前で突然患者が苦しみ始めたのに、「よーし、17時になったからかーえろっ♪」なんてことできるわけがありません。そこで、医師には今回このような時間外労働を定めました。しかし、救急医療など人手がかなり必要になる医療分野、または初期研修医・後期研修医などまだまだ駆け出しで学ばなければならないことが多くある人たちには年1,860時間以下/月100時間未満と規定が緩くなっています。
どうでしょうか?多すぎるよ!って思いますか?たしかに年960時間ということは月に80時間、1ヶ月の勤務日を25日とすると、毎日3〜4時間の時間外労働をしているという計算になりますね。年1,860時間なんていったら約2倍の時間になります。
それだけ医師が必要とされているということが実感できるかと思います。
②時間外割増賃金率が50%以上の引き上げ
2023年からは、医療界も含めて中小企業において、月60時間を超える時間外労働をした場合に50%以上の割増賃金率で計算して給料を支払わなくてはなりません。時間外割増賃金率を引き上げることで、雇う側はなるべく1人当たりの労働時間を短くしようとします。これにより時間外労働を軽減できるというのが狙いです。
「働き方改革」は医師だけでなく、患者さんにもメリットがある
命を預かる職業である医師が、長時間勤務で疲弊しきった状態で仕事をすると、重大なミスを犯して患者さんの命に危険が及ぶ可能性が高まります。
そのため、医師に過度な勤務をさせないことは重要です。
患者さんも安心・安全な医療を望んでいるので、この取り組みは患者さんにとってもメリットは大きいと思います。
一方、地方では人材不足に悩まされているケースもありますし、研修医など若手医師は長時間働くことで知識や技能を獲得できることから、長時間勤務を必ずしも否定できないというのも現状です。
そこで、医師の勤務時間の上限は、年間960時間の時間外労働と定められました。
地域医療に従事する医師や研修医など若手医師は1860時間までの時間外労働が許容されます。また、連続勤務を28時間以内とすることや勤務間のインターバルを9時間取ることなどが定められました。
しかし、それでも一般企業よりは緩い規則になっていますし、過労死ラインを超えるような水準であることに変わりはありません。医師の健康管理と人員確保の両立が今後の課題となりそうです。
働き方改革についてもっと知りたい方は下のリンクもご参照ください。
「働き方改革」は日本の医療を維持するためにも必要
医師の働き方改革についての特設サイトが、厚生労働省から公開されています。
わかりやすく解説されていますので、気になる方はチェックしてみてくださいね。
少子化高齢化が進む現在の日本においては、医師が働き続けることが可能な環境づくりが重要になります。
今後、さらに医師の労働環境が改善され、誰もが働きやすくなることを願ってやみません。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。










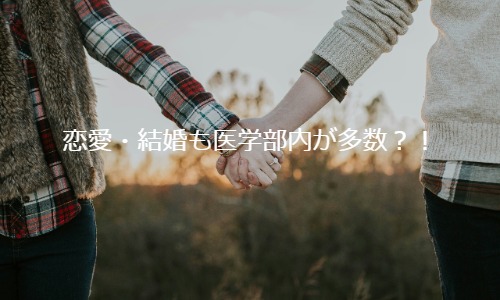

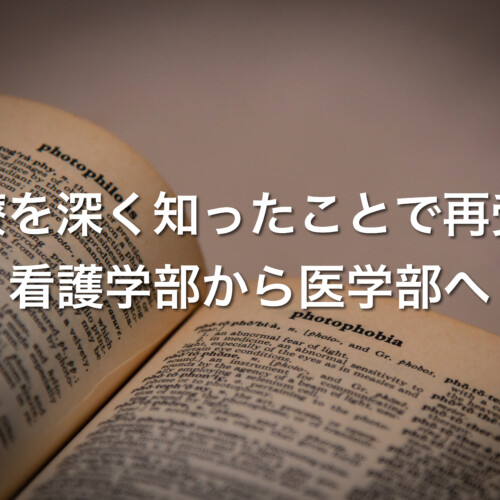
この記事へのコメントはありません。