受験勉強はメリハリが重要!タイマー計測で時間を区切るのがおすすめ

勉強をしてる時夢中になって、休憩もせずに長時間勉強をしている時はありませんか?
長時間勉強する方が、たくさん勉強できて良い!と思われるかもしれませんが、実は適度に休憩をとってメリハリをつけた方が集中力を保つことができるんです!
今回は、勉強をする際の時間配分についてご紹介します。
Contents
休憩を取る方が効率的に勉強できる

休憩をとった方がいいとはいえ、休憩を取らない方が長時間勉強できて良いと思うかたもいるでしょう。休憩は取ったほうがよいというデータをご紹介します。
同じような学力の中学1年生を、3つのグループに分けて、英単語を覚えてもらいます。
1つ目のグループは、60分休憩なしで勉強します。
2つ目のグループは、45分休憩なしで勉強します。
そして、3つ目のグループでは、15分かける3セット、7.5分の休憩を2回とって、勉強します。
1週間後の英単語を覚えているかどうかテストした結果、休憩をとった3つ目のグループの点数が最も高かったのです。
つまり、休憩を取らずに勉強するよりも、休憩をして勉強するほうが、効果的に勉強できる可能性が高いのです!
「学習時間を細かく分けた「45分」で「60分」と同等以上の学習効果を発揮 “長時間学習”よりも短時間集中の“積み上げ型学習”が有効であった」については以下のリンクカードをクリック。
オススメの休憩サイクル3選
そうはいってもいつ休憩すればいいかわからない。そんなみなさんに、いくつか休憩するサイクルを紹介します。
①学校に合わせる。
通っている学校の、授業時間に合わせて休憩する方法です。その場合、家で勉強するときも、そのサイクルで勉強します。いつも慣れ親しんでいるサイクルを活用すれば、勉強に集中しやすいかもしれません。
②ポモドーロ法を試す。
ポモドーロ法とは、1990年代にフランチェスコ・リシロ氏が作った、タイムマネージメント法のことです。
ポモドーロ・テクニックの手順はとっても簡単。
1)やりたい課題を選ぶ
2)タイマーで25分セットする
3)タイマーがなるまで課題に取り組む
4)5分程度の短い休憩をする
5)2~4を4回繰り返したら(おおよそ2時間たったら)、長めの休憩を取る。
このステップに従って、作業をするだけです。
ぜひ、試してみてください。
「ポモドーロ・テクニック再入門ガイド|すぐできる生産性アップ術」については以下のリンクカードをクリック。
③15分•45分•90分の法則を試す
人間がとても深く集中できる時間は15分。また、人間の脳のリズムは90分毎であり、その中で覚醒と非核覚醒が繰り返しているそうです。集中力できる時間を延ばすことは難しいので、長くても90分が集中できる限界といえそうです。
おすすめの休憩サイクルを3つご紹介しました。科目によって休憩サイクルを変えるのもおすすめです。
ポモドーロ法をもとに勉強を行うと、暗記科目ではよいかもしれませんが、数学や理科などの考える問題を行っているときは、25分という時間はすぐにたってしまいますし、考えている途中になってしまうこともありますよね。そんな時は90分測って勉強するのが良いと思います。
だらけ防止に役立つ休憩ルール
休憩が重要なことはわかりました。しかし、そうはいっても休憩をとっているうちに、ついついだらけて勉強に戻れない。そんな悩みを持っている人も多いでしょう。
ということで、休憩ルールの具体例を紹介したいと思います。
ルール① タイマーをかける
時間を決めないで休憩していると、いつのまにか勉強していないなんてことに。
そこで、休憩する時間を決めてタイマーをかけましょう。休憩時間が終わると、タイマーが鳴るので、メリハリがつけやすいです。勉強する時間と、休憩する時間をきっちり分けて効率よく勉強しましょう。
ルール② 周りに遊ぶものを置かない。
休憩しようと思って、スマホを少し見る。気がついたらゲームをして1時間経っていた。そんなことはありませんか。私はしょっちゅうそういうことを繰り返していました。その解決方法は、休憩する場所の近くにスマホやゲームなど遊ぶものを置かないということです。物理的に位置を離すのが一番の解決方法です。休憩するときは、周囲に気を引かれるものがないように、スマホは予め離しておきましょう。
タイマーを使った勉強のメリット3選
①勉強にメリハリをつけることができる
タイマーで時間を測って勉強時間を区切ることで、勉強にメリハリをつけることができます。
一般的に、人間の集中力が続くのは最大で90分までと言われていて、人によってそれより短い時間であることも多々あります。
確かに、試験の時など、一時的になら長時間勉強することもできるかもしれませんが、合計して長い時間、質の高い勉強をするためには、適度に休憩を取ることが大切です。
また、勉強時間と休憩時間をはっきりと分けることで、ON/OFFの切り替えをすることができます。
このように、タイマーを使用することで、強制的に勉強時間を区切り、結果的に勉強の効率を高めることができます。
勉強時間を区切る効果についてはこちらの記事で詳しく解説されていたので、興味がある方はご覧ください。
②科目間の勉強時間のバランスを取ることができる
タイマーを使って勉強することで、科目ごとの勉強時間のバランスをとることができます。
受験生の中には、特定の科目の勉強に熱中して他の科目が疎かになってしまうことに悩んでいる人もいるのではないでしょうか?
私が受験生の頃は、数学の解けない問題を考えていると夢中になって数時間経っていたということがあったのでタイマーで何分考えると決めてタイマーを鳴らしていました。こうすると、意識的に勉強時間をコントロールできるようになります。
さらに、勉強時間を記録すれば、後から振り返ることで勉強計画も立てやすくなります。
③スマホで気が散るのを防ぐことができる
いつも持ち歩いているスマホのアプリをタイマーとして利用している受験生もいるかもしれませんが、受験生なら断然タイマーがおすすめです。
スマホアプリのタイマーを使っていると、ついつい通知が気になったり、タイマーを操作するときに他のアプリが見たくなったりしてしまいます。
勉強用のタイマーを用意することで、不必要に気が散ってしまうことを防ぐことができます。
受験生のタイマー選びのポイント
では、実際にタイマーを選ぶ際、どのような機能に注目して購入すれば良いのでしょうか?ここでは、勉強に使うタイマー選びのポイントをご紹介します。
タイマー機能とストップウォッチ機能の両方があるか
受験勉強に使用するタイマーの選び方のポイントの一つ目は、タイマー機能とストップウォッチ機能、つまりカウントダウン機能とカウントアップ機能の両方がついていることです。
タイマー機能は言うまでもなく、時間を測って問題を解くときに必要ですね。それに加え、ストップウォッチ機能も、勉強の上で大いに活用しましょう。勉強を開始するときにスタートし、解くのにかかった時間を測ったり、科目ごとにどのくらいの勉強時間をかけているのか、バランスを把握したりするのに使うことができます。
消音機能があるか
キッチンタイマーなどでは、タイムアップ時にアラーム音が鳴って時間終了を知らせてくれることが必須です。
しかし、勉強の時に使用するタイマーではむしろ消音機能が必要になります。これは、図書館や自習室、カフェなど、音を出せない環境でも使用するためです。 アラーム音がoffにでき、光やバイブレーションで時間を知らせてくれる機能がついたものを選びましょう。
最大の設定時間の長さ
勉強に用いるタイマーでは、何時間まで測ることができるかも重要になります。中には60分までしか測れない製品もあり、長い間勉強時間を計測したい場合など、用途に応じてしっかり確認必要する必要があります。
最大の設定時間は製品の公式サイトなどで見ることができるので、購入前にチェックするようにしましょう。
快適に使えるデザインか
勉強のお供として頻繁に使うことになるタイマーなので、「見やすさ」「操作性」「大きさ」「見た目」なども選ぶ時のポイントになります。
使いやすさやデザイン性など、重視したいポイントで選びましょう。
時間がすぐわかる方がいいという人はディスプレイが大きいものがおすすめ。逆に数字が見えすぎない方がいいという人はある程度小さいものを選ぶのが良いでしょう。
もちろん操作性も大事ですね。例えば、数字のボタンがついているものを選べば時間設定が簡単にできます。
また、図書館や自習室、カフェなどの自宅以外の場所でも使うという人は自分がストレスなく持ち歩くために、サイズも重要になってきますね。小さいサイズのタイマーを選ぶとどうしても文字盤も小さくなってしまいますが、筆箱などに入れて持ち歩くことも可能になります。
機能性だけでなく、見た目にこだわって選びたいならおしゃれで可愛いデザインの製品もチェックしてみましょう。自分のお気に入りのデザインのタイマー・ストップウォッチを使えば勉強のモチベーションもアップします!
受験勉強に使えるタイマー3選
TANITA デジタルタイマー バイブレーションタイマー クイック TD-370N
最初に紹介するのは、TANITAのデジタルタイマーです。
このタイマーのおすすめポイントは
・バイブレーション機能があり、図書館や自習室で使用しやすい
・タイマーとしてもストップウォッチとしても利用できる
・大きさが5.5cm×3.8cm×1.5cmと小さく、ペンケースなどに入れて持ち運びやすい
・タイマー、ストップウォッチ機能ともに最大設定時間が23時間59分59秒と長時間の計測ができる
などが挙げられます。
デメリットは
・スタイリッシュさに欠ける
・ディスプレイが小さい
ことがあります。
このタイマーは小ささや機能を重視したい人におすすめです。
商品詳細はこちらの公式サイトをご覧ください。
dretec T-587 ラーニングタイマー
次に紹介するのはdretecのT-587 ラーニングタイマーです。
このタイマーをおすすめする理由は
・画面が斜めになっていて、置いた状態で見やすい
・消音設定が可能で、光で時間を知らせてくれる
・タイマー、ストップウォッチ機能ともに最大設定時間が199時間59分59秒と長時間の計測ができる
・デイタイマー機能があり、テストまでの日にちのカウントダウンができる
・カラーバリエーションが豊富
などがあります。「ラーニングタイマー」の名前通り、勉強用として使いたいポイントがたくさん詰まっていますね。
デメリットは、
・サイズが8.0cm×6.0cm×2.3cmで、少し大きく、持ち運びや卓上でのスペースをとる
・操作ボタンが4つなので直感的な操作ができない
ことが挙げられます。
大きいSTART/STOPボタンが特徴で、タイムトライアルをしたい人にもおすすめです。
商品詳細はこちらの公式サイトをご覧ください。
MAG 消音・音量切替機能付きデジタルタイマー XXT504
最後に紹介するのは、MAGのデジタルタイマーです。
このタイマーのおすすめポイントは
・タイマー、ストップウォッチ機能がある
・消音(ライト点滅)の設定ができる
・ディスプレイが大きい
・10分、1分、10秒のボタンがついているので時間設定がしやすい
・スタンド、マグネット、ストラップホール付きで、置く、掛ける、貼ると三通りで使える
などがあります。 一方で、デメリットとして、
・最大設定時間が99分程度と短い
・サイズが9.5cm×6.5cm×2.0cmで、少し大きく、持ち運びの際にスペースをとる
などが挙げられます。
長時間の計測には使わない大きくて見やすい画面がいい、時間設定を素早くしたい、という方におすすめです。
https://www.mag-clock.co.jp/product/search/index.php/item?cell003=その他&cell004=デジタル温湿度計&label=1&name=音量切替機能付きタイマー&id=24
効率よく勉強しよう
今回は勉強する際には、メリハリを付けることでより効率的に勉強出来るということをお伝えしました。
とはいえ勉強しているとついつい熱中してしまって、時間を忘れてしまいがちです。タイマーを使うことで時間が来たことを分かりやすくして、効率的に勉強してみてください。
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。








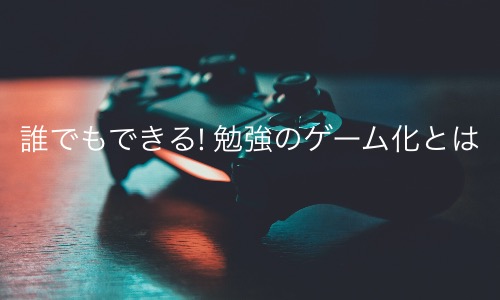
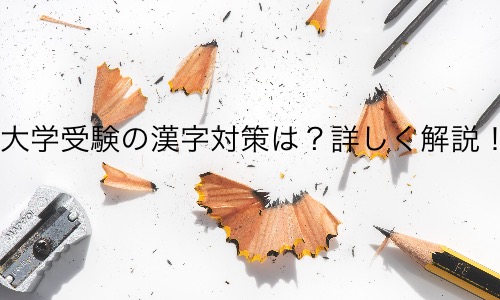



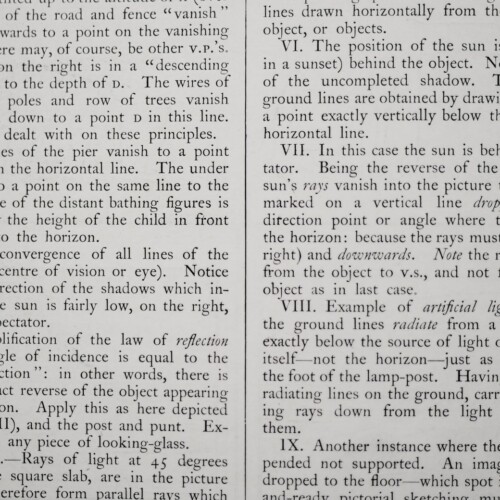


この記事へのコメントはありません。