医学部志望におすすめの大手3大記述模試(ベネッセ・河合塾・駿台)を比較しました!
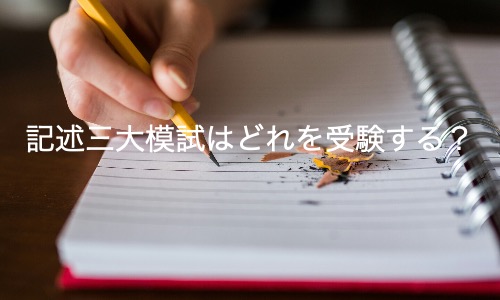
大学受験を意識し始めると気になってくるのが「模試」の存在。
模試を受けていると、模試のレベルの違いを感じませんか。
この模試では偏差値70、でも違う模試では偏差値50だった。そんなこともあるかもしれません。また、共通テスト模試と記述模試では、問われる知識は同じでもそれをどう問題に活かすのかが違うので、模試ごとに分析が必要です。
今回は、ベネッセ、駿台、河合塾の代表的な記述模試を比べて、それぞれの模試のレベルがどれくらいかを調べていきたいと思います。
Contents
模試は高1からの受験がおすすめ

まず、最初に模試を受ける学年ですが、大学受験を見据えている場合、模試は高校1年生から受験することをおすすめします。
「まだ本格的な受験勉強なんて何も始めていないよ?」と思われるかもしれませんが、模試を受験することには後述するようにいくつものメリットがあり、毎日の勉強に活かせる部分がたくさんあるからです。
高1で既に行きたい医学部が決まっていれば、志望校の欄に書いてみましょう。
部活が忙しくて模試を受けに行く時間がなかなか取れない……という人も、2年生には模試を受けておくと、よりよい受験勉強のスタートが切れるでしょう。
模試を受ける頻度はどうすれば良いでしょうか。
結論から言うと、模試は
・高校1、2年:4ヶ月に1回以上 ・受験生:2ヶ月に1回以上
のペースで受けるのが良いと思います。特に受験生は、自分の学習の進捗を頻繁に確認して、目標の修正に役立てるのが良いので2ヶ月に1回以上としています。
模試を受験すると1日潰れてしまうことが多いので、たくさん模試を受けることよりも、「模試の結果を生かした復習をしたり、勉強計画を立てられる」間隔で受験することが大切です。
模試受験で自分の立ち位置を確認できる

模試を受ける一番の目的は、「現在、自分が受験生の中でどのレベルにいるのかを知る」ということです。
長く大変な受験勉強。合格できそうかわからないまま闇雲に頑張るのは、精神的につらいですよね?
模試を受けることで、同じ大学を志望する受験生の中で、自分がどれくらいの立ち位置にいるのかを知ることができます。
普段の学校内の試験では学年内順位・クラス内順位しか分かりませんが、模試では全国の高校生が同じ問題を受けます。
高校の偏差値や定期試験の難易度が高い場合は「学校内での順位はさほどでもないけれども、全国的に見れば結構いいレベルにいた」ということもありますし、逆に大学進学を目指す人があまりいない学校だと「学校内ではトップだったのに、全国的に見ればそうでもなかった」というケースもありえます。
入試では全国のライバルを相手に戦うため、「学校内でどのくらいの立ち位置なのか」よりも「全国でどのレベルなのか」を見る必要があります。
模試を受け、偏差値や志望校の判定を見ることで、「自分は今現在、全国でどのくらいの立ち位置なのか」「同じ志望校を目指す高校生の中でどのくらいの順位なのか」の目安を知ることができるのです。
模試は同じ会社のものを継続して受験する
重要なのは「同じ予備校の模試を連続して受験する」ことです。
塾や予備校によって偏差値や志望校の判定などには癖がありますし、受験者も異なっています。
そのため、違う予備校の模試を受けてしまうと「前回の模試に比べて、今回はどうだったのかな」という比較がしづらくなってしまいます。
勉強計画を立てるときは、「偏差値を65にしよう」「遺伝の問題をマスターしよう」などの目標も同時に立てているはずです。
模試を受けることで、目標を達成できているかどうか、あるいは目標達成への途中経過を確認できます。
偏差値や単元、問題形式など自分の目標に合わせた部分のデータのみを比較することで、自分の予定通りに成績が伸びているか、苦手部分を克服できているかをチェックしてみましょう。
思ったとおりに成績が変化していれば「効果のある勉強をできている」ということなので、計画通り勉強を進めればいいことが分かります。
予定したとおりに成績が伸びていないのであれば、なぜうまく行っていないのかその理由を探して改善しなくてはなりません。
「進研模試」は10以上偏差値が高くなるので注意
1つだけ注意したいのが、「学校で進研模試を受けている」という場合。
進研模試は問題が易しく、そして他の模試と違って「受験を目標としない」生徒が多い学校にも多く採用されている模試です。
10〜15ほど偏差値も高く出てしまうため、「自分の成長をはかる」「全国的な自分の立ち位置を知りたい」という目的にはあまり適しません。
大学受験を目指しているのであれば、進研模試以外にもこれからご紹介する大手予備校の模試を受けることをおすすめします。
ベネッセ・河合塾・駿台の3社を比較
「模試を受けよう」と思った時に気になるのが「どの模試を受験すればいいのだろうか」ということ。
先程も述べたように、模試では現在の自分の立ち位置を知ることが大切です。そのためには、自分と同じレベルの人、自分が志望する大学の受験生がたくさん受けている必要があります。
一般的な難易度は、ベネッセ>河合塾>駿台と言われています。
ここからは具体的な模試模試の名前とないようをご紹介します。受験生のほとんどが受けるといっても過言ではないような模試ばかりです。受験を見据えて記述型の模試に加えてマーク模試も少なくとも1つずつは受けておくことをおすすめします!
医学部志望なら年1回は受験したい「駿台全国模試」
おすすめ度:★★★☆☆
難易度:難
駿台生が裏で「残酷(ざんこく)模試」とか「soon die(すーんだい)模試」と呼んでいるのがこのテストです。かなり厳しいテストです。こちらの模試は高校1年生から受験可能です。
どのくらい厳しいかというと、他の模試よりも偏差値が5~10低く出ると思ってもらっても構わないくらい。
駿台が実施する模試の特徴としては、学力上位の受験生が受けるということです。母集団の学力が高く、難関大学を目指す学生が多く受験します。もし、国公立大学、難関私大を受験したい場合は、ベネッセなど受験者の多くが難関大学を受けない模試を受けても、自分の位置がよくわかりません。駿台の場合は、模試を受ける受験生の多くが難関大学を志望しているので、難関大学を志望している受験生はぜひ受けましょう。
私の受験生時代の印象としては、1)ひねられた問題がでる。2)マニアックな知識をたまに問われる。3)偏差値は低くでがち。という感じです。一癖ある問題が好き、受験テクニックを思う存分使いたいという受験生は駿台の模試が好きかもしれません。
駿台生は自動的に受けることになっていると思いますが、外部生はあまりに難しいから受けないという声も聞いたことがあります。
ただ、「未知の難易度に遭遇した時」の対処法を探るという意味でも1回は受けておいてもいいかもしれません。
また、この模試は浪人生も数多く受ける模試です。浪人生は一度、受験をしていることもあり現役生の手が回らない理科や社会も一通り終えて挑んできます。難関大や医学部受験生が、自分の正しい立ち位置を知り、このままではまずいと危機感を持つためには良い模試だと思います。
年3回のペースで受験する定番の「河合全統記述模試」
おすすめ度:★★★★★
難易度:難関大標準レベル
記述模試では、自分の力で問題の情報を整理し、解く力を計ることができます。また、高校1年生から受験可能です。
見たことのない問題や形式がまばらな問題に対しての対応力・解答力が露呈するので、完全な実力を知りたい、という人にはおすすめです。
私の受験生時代の印象としては、1)あまり問題がひねられてない。素直な出題。2)出てきた偏差値が一番信用できる。3)全統模試で解けなかった問題は復習必須。という感じです。駿台ほどクセがなく、逆にいうと全統模試で上手くいかない教科や分野は非常にヤバいという印象でした。
特に医学部受験では、記述型の試験のことも多いので、本番に近い形の試験を受けることができます。
医学部志望なら敢えて受験しなくてOK「ベネッセ」
おすすめ度:★★☆☆☆
難易度:大学受験標準レベル
基本的に学校から指示があって受けるテストという印象が強いと思います。それもそのはず、進研模試/ベネッセ総合学力テストは個人からの申込みを受け付けていません。ベネッセ、駿台が合同で行っているベネッセ・駿台模試以外は、基本的に学校が申し込んで受けるものだと思います。
このベネッセが主に運営しているテストの特徴は、ともかく受験者人数が多いことです。大学、短大進学を目指す、全国約45万人が受験します。ほとんど全ての大学受験を目指す受験生が受けています。
私が現役のときにベネッセに感じていた印象は、1)問題は教科書を中心にでる。教科書に基づいていて、そこから外れることはあまりない。2)受験者層が幅広いので、思ったよりも偏差値が高く出る。といった感じでした。
ベネッセの模試について、詳しく知りたい方は以下のリンクをご参照ください。
「各大学別の冠模試」も活用しよう
おすすめ度:★★★★☆
難関国立大学では、その大学の入試に寄せた問題がでる模試が用意されています。
冠模試の合格判定は、その大学を受けるほとんどの受験生が受けるので、かなり正確だといわれています。
冠模試は、旧帝や東京科学大、神戸大などで実施があります。(統合前の医科歯科)
各大学別の模試は、正直どこの予備校もそこまで難易度の差は無いように思います。また、形式も当然同じですが受験者数の多い大手の河合、駿台あたりがおすすめです。
合格基準から見ても模試レベルには差がある

合格基準から、模試のレベルの差を見ていきたいと思います。ベネッセからは7月に実施された「進研模試 総合学力記述模試」、駿台は5月に実施された「駿台全国模試」、河合塾からは「第2回全統記述模試」を出し、合格基準をもとに偏差値を比べていきます。それぞれの模試でA判定やC判定がでる偏差値にかなり違いがあります。
| 模試名 | 判定 | 東京大学 理科3類 前期 | 慶応義塾大学 法学部 法律学科 |
| 進研模試 総合学力記述模試 | A判定:合格可能性80%以上 | 88 | 85 |
| 進研模試 総合学力記述模試 | C判定:40%以上60%未満 | 85 | 78 |
| 駿台全国模試 | 合格可能性80% | 79 | 64 |
| 第2回全統記述模試 | 合格可能性が50%になるライン | 72.5 ~ 74.9 | 67.5 ~ 69.9 |
(ベネッセ「進研模試 判定基準」、リセマム「【大学受験2024】駿台全国模試<私立>大学別合格目標ライン」「【大学受験2024】駿台全国模試<国公立>大学別合格目標ライン」、河合塾「合格可能性評価基準一覧」より作成。)
例えば、慶応義塾大学法学部法律学科を目指している場合、進研模試では偏差値85以上でA判定が出ますが、駿台全国模試では偏差値79以上でA判定が出ます。
模試の結果には一喜一憂しない!
模試のレベルによって偏差値は違います。
偏差値は、その模試を一緒に受けた他の受験者に影響を受けます。
ですので、偏差値や順位などの数字に一喜一憂しすぎずに、どの問題ができなかったのか、どの分野でのびしろがあるのかに注目しましょう。
模試はあくまでも通過点にすぎません。模試では良い成績でも本番で力が出し切れるかどうかは誰にも分からないのです。
模試は受験するだけでも体力が消耗すると思いますが、頑張って乗り越えましょう!
コメント ( 0 )
トラックバックは利用できません。





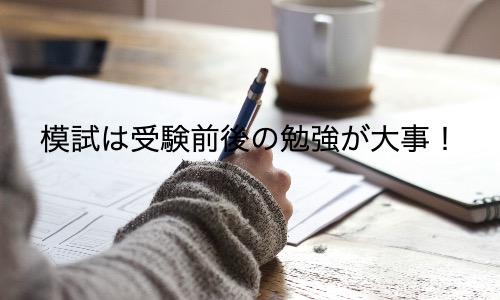
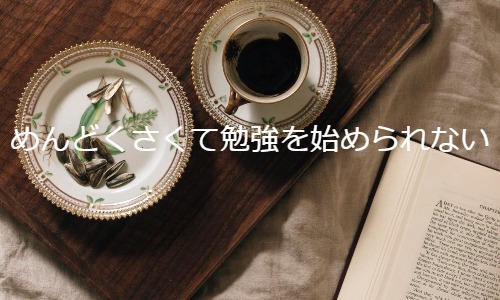
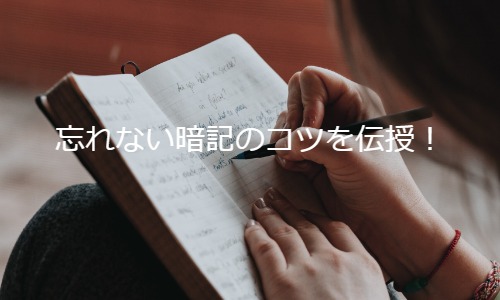
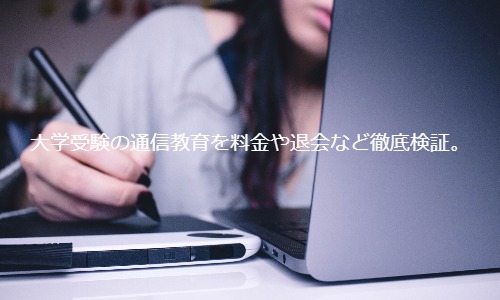



この記事へのコメントはありません。